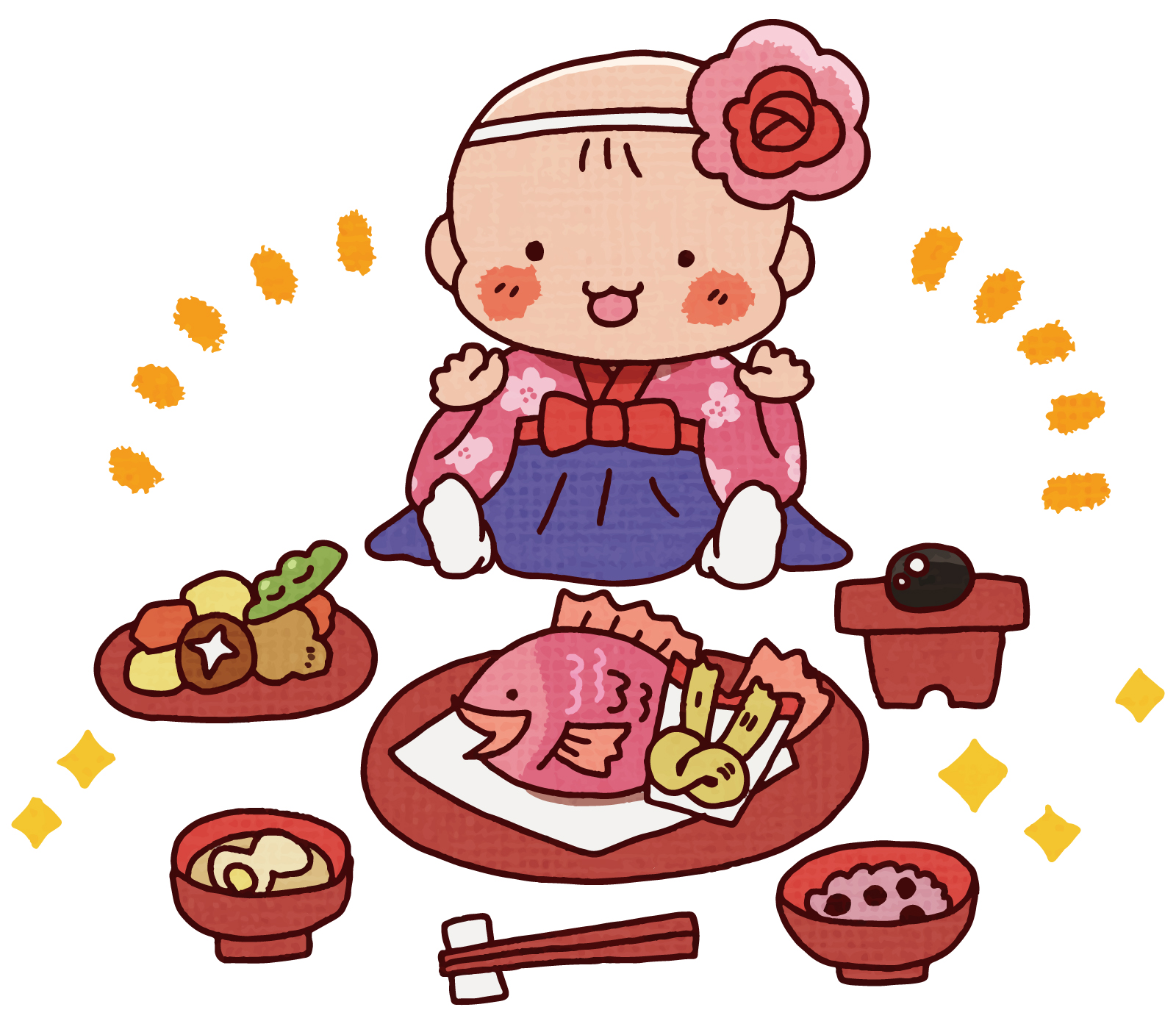赤ちゃんが生まれたことを土地の氏神様に報告してお祈りするお宮参りと、赤ちゃんが将来食べ物に困らないようにと祈願するお食い初めは赤ちゃんとパパママにとって大事なお祝い事ですよね。
しかし、本来別々の時期に行うこれらをお家の事情などで一緒にやろうと思っても、どのように進行したいいいか悩みどころですよね。
ここでは、お宮参りとお食い初めを一緒にやる場合のメリット・デメリット、一緒にやる場合のポイント、おすすめのスケジュールの組み方を紹介します!
お宮参りとお食い初めを一緒におこなうことは可能?

お宮参りとは地域によって行う時期が変わりますが、大体生後30日以降に神社にお参りしてその土地の氏神様に赤ちゃんの誕生を報告して健やかな成長をお祈りする行事です。
そして、お食い初めとは生後100日を過ぎたら赤ちゃんが将来食べ物に困らないようにとの願いを込めて行う行事です。
この2つの行事は行う時期が離れていますが、一緒にやることは可能です。
今は様々な事情からお宮参りをお食い初めの時期と一緒におこなうお家が増えています。
お宮参りとお食い初めを一緒にやるメリットとデメリット
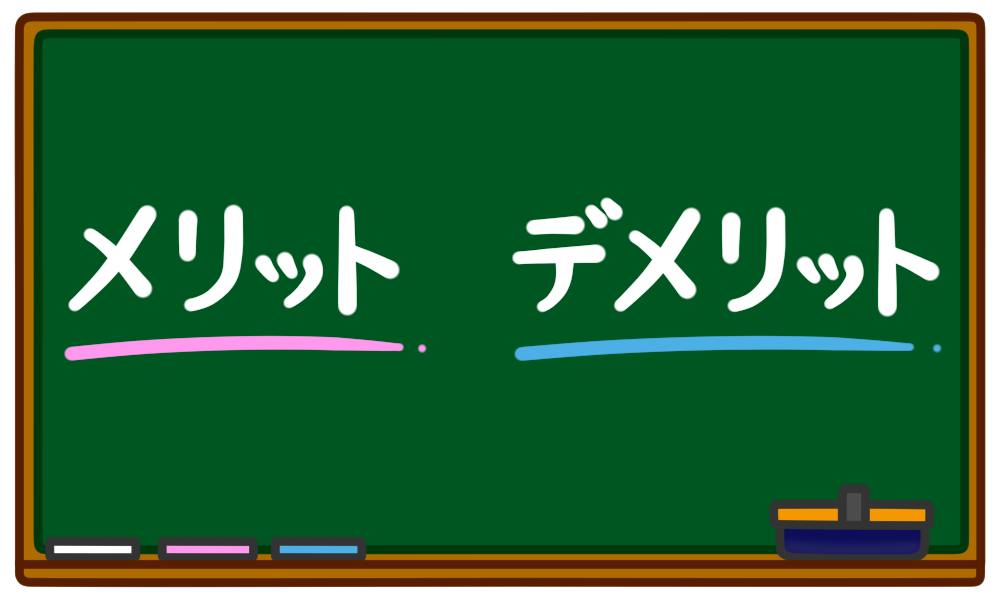
2つの行事を一緒にやることでどのようなメリット・デメリットがあるのか紹介します。
メリット
赤ちゃんとママの体調が安定しやすい
お宮参りをする時期は主に生後30日前後となっているのですが、その時期はまだまだ赤ちゃんはデリケートなので少しの刺激で体調を壊してしまう可能性があります。
また、産後のママの体調も落ち着かない時期なので、無理をしてしまうと産後の回復が遅くなってしまうことがあります。
お食い初めは生後100日以降の行事なので赤ちゃんの体調とママの体調が安定しやすくなります。
パパママの両親など親戚がお祝いに集まりやすい
両家の親戚の方たちも赤ちゃんの誕生をお祝いしたいという気持ちが強いですよね。
しかし、行事が別れていると予定を調整するのが大変なときもあります。
パパママの両親や親せきの方の招待を考えている場合は、2つの行事を1回で済ますことでそういった親戚の方が参加しやすくなります。
費用を減らすことができる
赤ちゃんのお祝いの行事は大変うれしいものでおめでたい物ですが、費用が掛かってしまうことが多いです。
親戚の方の招待を考えている場合はその方たちの食事の費用などもかかることがあるので、複数回おこなうと費用がかさんでしまいます。
しかし、行事を一緒にやることでそれらの出費が1回で済むので費用を減らすことができます。
デメリット
赤ちゃんの成長過程を飛ばしてしまう
赤ちゃんは日に日に成長していくので、生後30日ごろの赤ちゃんと生後100日ごろの赤ちゃんとではまた別の可愛さがあります。
そのため、一緒にお祝いするよりも別々でお祝いして記念の写真を撮ったりすることで、より赤ちゃんの成長過程を時間できます。
こう考えると一緒にやることに勿体なさを感じてしまうことがあるかと思いますが、お家の都合や赤ちゃんとママの体調を考慮して別々に行うか、一緒にやるかを決めましょう。
2つの行事の準備で忙しくなってしまう
お宮参りもお食い初めの準備を一緒にすることで、やることが増えてしまうので大変と感じてしまいます。
お宮参りの準備は参拝に適した赤ちゃんの服やパパママの服、初穂料の準備やご祈祷の流れを神社に問い合わせたりなどがあります。
お食い初めはお家でやる場合は御膳の準備、食器、参加者用の食事の用意が必要で、外食の場合はお店の予約などの準備があります。
別々に行うよりも準備がハードになってしまうのでパパママとで分担して準備することでスムーズに準備しやすきなります。
お宮参りとお食い初めを一緒にやる時のポイント
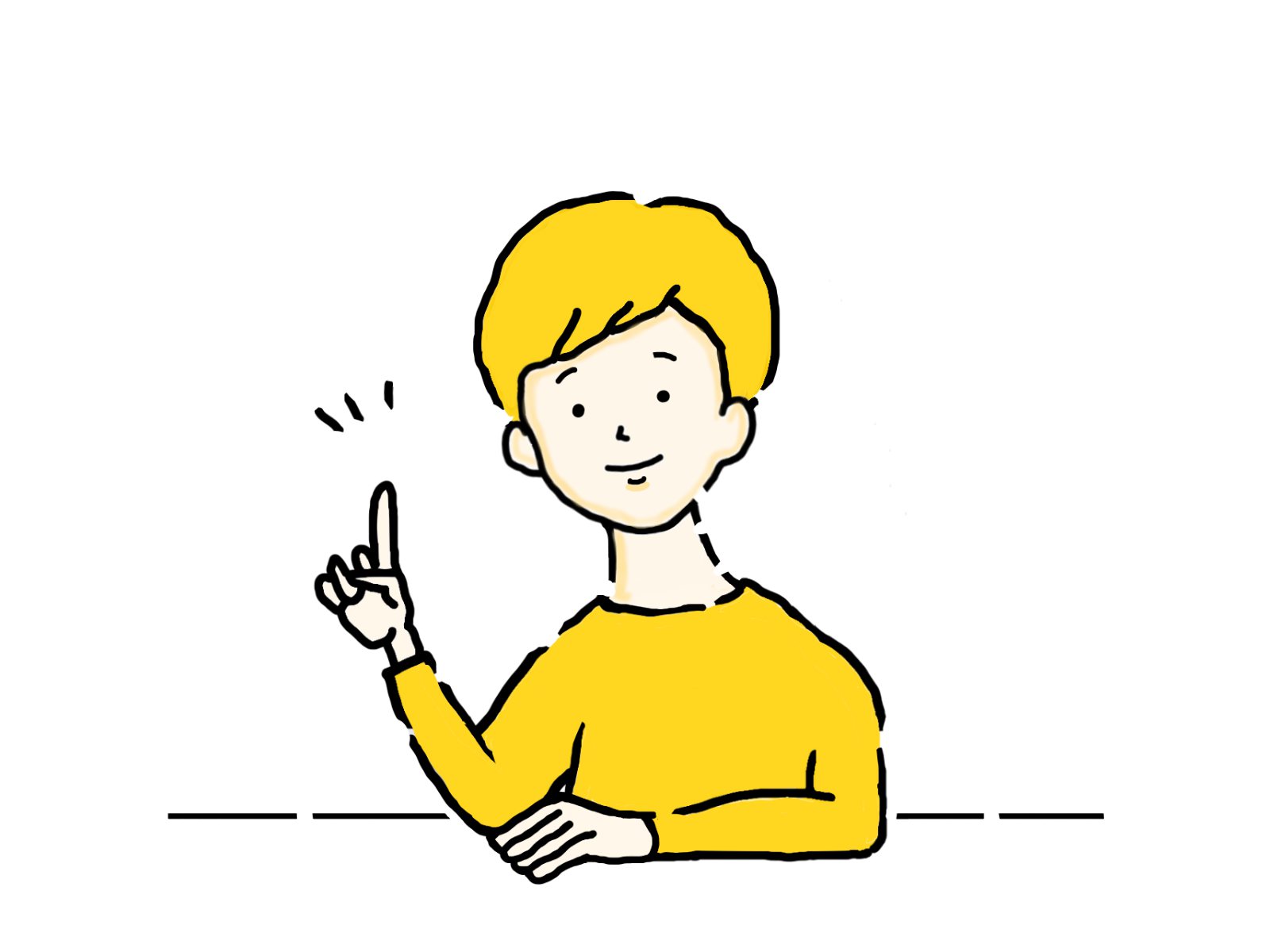
2つの行事を一緒におこなう時のポイントを紹介します。
地域、家族の風習を確認しておく
お宮参りやお食い初めは地域の風習によって違いがでることがあります。
また、地域の風習とは別に家族で受け継がれてきた風習があることもあります。
その場合は、無理に地域の風習を採用する必要はないのでパパママ、両家の親族の方と相談して決めておくとスムーズに事が運びやすいです。
当日の準備を減らす
2つの行事を一緒にやる場合はお祝い当日にすることを減らすことでスムーズに行事を進めやすくなります。
お宮参りでご祈祷をお願いする場合は初穂料を神社に納めなければなりません。
当日にお金をのし袋に納めたり、赤ちゃんの名前などを書いたりするとスケジュールがおしてしまう可能性があるので、前日までに準備しておきましょう。
お食い初めの御膳を準備する場合は、当日に作るとバタついてしまう可能性があるので前日に料理の仕込みをしておくことでスムーズに出すことができます。
また、外食の場合も混雑を想定して早めに予約をしておきましょう。
スケジュールは無理なく立てる
同じ日に2つの行事を行うとずっと動き通しになってしまう可能性があり、パパママの体力が必要になってきます。
特に、赤ちゃんの体力と産後から100日以上たったとはいえママの身体は万全とは言えない状態です。
神社と撮影所が離れている場合は移動の時間なども計算に入れておくと余裕をもつことができます。
赤ちゃんのおむつ替えや授乳などのことも加味して無理のないスケジュールにならないように余裕をもって組みましょう。
お宮参りとお食い初めを一緒にやる時のおすすめスケジュール

2つの行事を一緒にやる時のおすすめのスケジュールの組み方を紹介します。
撮影は最初にする
記念撮影を予定している場合は一番最初にしましょう。
行事の最期に写真撮影をすると、疲れから赤ちゃんが不機嫌になってしまって撮影がうまくいかないことがあります。
行事の一番最初にすることで機嫌が悪くなりにくいので赤ちゃんの笑顔を引き出せる可能性が高くなります。
また、撮影前に授乳を済ましておくことで不機嫌になりにくくなります。
神社へお宮参り
神社へのお参りの行程は参拝のみとご祈祷でありで変わります。
参拝のみの場合は通常と同じようにお賽銭を入れてから鈴を鳴らし、二礼二拍手一礼で祈願します。
神主さんにご祈祷をお願いしている場合は、初穂料を神社に納めてお祓いと祝詞を上げてもらいます。
ご祈祷時間は大体30分前後であることが多いです。
しかし、参拝の時期によっては神社が混んでしまうことがありますので、時間に余裕をもって行動しましょう。
受付からご祈祷終了までの平均時間は1時間ほどです。
お食い初めをして食事会
最後にお食い初めと食事会をします。
お食い初めはお家(手作り、仕出しなど)、外食などで行います。
お家で行う場合は赤ちゃんも安心できる空間なのと外だと対応しづらいことも(おむつ漏れ、ギャン泣き)に対応しやすいのでパパママも安心できます。
外食で行う場合は個室のあるお店を選ぶと落ち着いた空間になるので、赤ちゃんも安心しやすいです。
お店によっては赤ちゃんのお食い初め用のコースを提供してくれているので事前に調べておくとスムーズに事が運びやすいです。
まとめ

- お宮参りとお食い初めを一緒にやることは可能です。
- お宮参りとお食い初めを一緒にやるメリットは赤ちゃんとママの体調を整えやすい、親戚の方が集まりやすい、費用を抑えられます。
- お宮参りとお食い初めを一緒にやるデメリットは赤ちゃんの成長過程を飛ばしてしまう、準備が2倍になってしまうことです。
- お宮参りとお食い初めを一緒にやる場合は風習の確認をして、当日準備を減らして無理のないスケジュールを組みましょう。
- スケジュールは記念撮影、お宮参り、お食い初めの順番がおすすめです。
以上が、お宮参りとお食い初めを一緒にやる場合のメリット・デメリット、一緒にやる場合のポイント、おすすめのスケジュールの組み方でした!
お宮参りとお食い初めを一緒にやるのはメリットもデメリットもありますが、赤ちゃんとママの体調や、パパのお仕事などの事情を汲んで決めていきましょう。
赤ちゃんのお祝いがいい思い出になるようにお祈りしています!